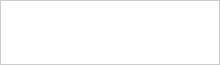今日の場面で主イエスは、必死になるべき一つの事柄を教えている。それは「救い」に関してである。場面は、神の国の福音を宣べ伝えながらの、エルサレムへの旅の途上の出来事である(22節)。主イエスは一つの講話を語られることになるが、それは一人の人の質問がきっかけとなっている(23節)。「主よ、救われる人は少ないのですか」。皆さんはどう思うだろうか。この質問自体は特別なものではなく、当時のユダヤ人たちの間で、良く取り上げられていた質問であった。ユダヤ教の教師(ラビ)は、この質問を良く受けたようである。当時、これに対して二通りの答えがあったようである。一つは、救われる人は多いというもの。「すべてのイスラエル人は来るべき世界に分け前を持つ」(ミシュナー)。選民のイスラエル人は皆救われるというもの。もう一つは、先の意見とは正反対である。「わたしは、今、わかりました。来るべき世に喜びを受けるのはごくわずかな人々であり、多くの人々は懲らしめを受けるのです」(旧約外典エズラ7章47節)。多い派から少ない派まで、混在していた。しかしながら、異邦人のことは余り念頭にない答えのようである。
では、主イエスはどう考えておられたのか。救われる人は多いと思っておられたのか。29節では「人々は東からも西からも、また南からも北からも」とあり、多いという印象を受ける。けれども、24節の「狭い門から入るように努めなさい。あなたがたに言いますが、多くの人が、入れなくなるからです」を読むと、救われる人は少ないという印象を持つ。他の福音書の箇所を読んでもそうなのだが、主イエスは、ある時は、救われる人は多いという印象のことばを語られ、ある時は、少ないという印象のことばを語っておられる。つまり、多い少ない両方を言っておられる。多いと言えば多いし、少ないと言えば少ない。主イエスは単純には答えていない。主イエスは、多い少ないよりも、あなたは救われる一人なのかと、自分の姿勢に関心を集中させようとしている。多い少ないの神学論議に熱を上げて、肝心なことに心を留めることを忘れてはならないわけである。救われる人の数に関心を持つこと以上に大切なことがある。あなた自身の問題として、救いを真剣に考えよ、ということである。
主イエスはある人の質問に対して、23節後半にあるように、「イエスは人々に言われた」と、聴衆すべてに語っていかれる。それは、救われる人の数について答えることが主眼ではないことは明らかである。それは一人ひとりに救われる姿勢について教えるものである。「狭い門から入るように努めなさい。あなたがたに言いますが、多くの人が、入れなくなるからです」(24節)。ここを読んで、マタイの福音書の山上の説教に、似たような教えがあることを思い出した方も多いだろう。「狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入って行く者が多いのです。いのちに至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そして、それを見出す者はわずかです」(マタイ7章13,14節)。マタイのほうでは、広く大きな門と狭い門の対比となっている。実は、マタイとルカでは、「門」と訳されていることばが原語では違っている。だから同じ「狭い門」と言っても、少し異なるイメージを持ったほうが良い。マタイで「狭い門」と訳されている「門」は、文字通り「門」である。カタカナにすると「ゲート」。だから、狭いと言っても、体をよじってどうにかしないと入れないような門ではない。ルカの「狭い門」の「門」と訳されていることばは、「ドア」「戸口」を意味することばである。25節で「戸を閉めてしまった」とか「戸をたたき始め」とあるが、この「戸」と訳されていることばと原語は全く同じである。だから「狭い門」を協会共同訳では「狭い戸口」と訳している。それは人一人がやっと入れるような狭さのドアである。ゲートではない。
以前、私は、ある建物に入ろうとした時、自動ドアが故障していて、自動ドアが人一人やっと通れるか通れないかの幅だけ開いていて、「故障中」の貼り紙が貼ってあった。私がそこを通り抜けようとしたら、「狭いので、あちらのドアからお通り下さい」と近くにいた従業員に言われた。私は、「大丈夫です。体が薄いので」と言って、そこを通り抜けたら、従業員の方は苦笑していた。このような狭いドアも、やがて閉じられてしまので、その前に、この狭いドアから入るように努めなさい、ということを主イエスはおっしゃったのである。
それにしても、「狭い門から入るように努めなさい」とはどういうことなのだろうか。狭くないという門もあるだろうけれども、それは悔い改めなくても、キリストを信じなくても、誰でも彼でも入れるような門だろう。しかし、それは滅びの門である。狭い門とは、キリストを信じ、キリストに従うことを意味するシンボルである。その門から入るように努めるとはどういうことだろうか。以前の新改訳第三版では、「努力して狭い門から入りなさい」と訳されていた。救いは、人間の行いによらず、人間の努力によらず、ただイエスをキリストと信じる信仰によるのではないだろうか。それは真実である。けれども、信じるとは、キリストに従うことによって全うされるものである。「努める」<アゴニゾマイ>は、「競技で賞を得るために戦う」とか「競技する」という意味のことばである。このことばが、他の箇所でどのように使われているか見てみよう。「競技をする人は、あらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです」(第一コリント9章25節)。「信仰の戦いを立派に戦い、永遠のいのちを獲得しなさい」(第一テモテ6章12節)。聖書は、この世の誘惑や試練に対して無防備でいいとは言っていない。雄々しく戦うように教えている。また信仰者を競技者にたとえ、奮闘努力するように教えている。「努める」という訳は、原語の意を汲んで、「奮闘努力する」でも、「必死に努める」でも良いだろう。「狭い門から入るように必死に努めなさい」ということなのである。
その狭い門から入るよう「必死に努める」という姿勢がない者はどうなってしまうのかが、続く「閉ざされた戸のたとえ」で教えられている(25~29節)。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまったら、もうアウトだよ、と教えられている。25節の「家の主人」とは、家の事柄に関して一切の権限を握っている。このたとえでは、主イエスを指す。「戸を閉める」とは、「錠を下した」という厳しい表現が採られている。錠を下してしまったら、戸をたたいても、泣いてわめいても、もう入れてもらえない。この家の主人が戸を閉めるという表現に、ノアの洪水の時のことを思い出す。ノアは箱舟を造りながら、洪水という神のさばきの日の訪れのことを住民に伝えた。けれどもノアの箱舟に入ったのはノアの家族八人だけであった。そして、こう言われている。「主は彼のうしろの戸を閉ざされた」(創世記7章16節)。戸を閉ざしたのはノアではなく、主なる神であった。ジ-エンド。そして全地にさばきが下った。この世の終わりのさばきの時にも、同じようなことが起きる。
26節には、それでも泣きついて食い下がろうとする人々の声がある。「私たちは、あなたの面前で食べたり飲んだりいたしました。また、あなたは私たちの大通りでお教えくださいました」。主イエスと食卓をともにしたユダヤ人たちがいた。また多くのユダヤ人が会堂だけではなく大通りでも主イエスのことばを耳にした。けれども、あの時一緒にいたでしょ、あなたの教えを聞きましたよ、と言っても何にもならない。それは現代人も同じことである。聞いただけで、それで終わってしまっては、神の国に入る資格は生まれない。一時は、主イエスに従う姿勢を見せたかもしれないが、昔に舞い戻ってしまっては、何にもならない。
27節は、家の主人の絶縁宣言である。「不義を行う者たち」とあるが、主イエスを見た、主イエスに接した、主イエスのことばを聞いたと言っても、悔い改めがないならば無駄であるとわかる。また名目上のクリスチャンも危ういということがわかる。この時の聴衆はユダヤ人であったが、もちろん、ユダヤ人であるというだけで救われるわけではない。
「あなたがたは、アブラハムやイサクやヤコブ、またすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分たちは外に放り出されているのを知って、そこで泣いて歯ぎしりするのです」(28節)。「アブラハム、イサク、ヤコブ」はユダヤ人の族長であるが、自分たちが肉体的にアブラハムの子孫というだけで救われるのではないことをはっきりと教えておられる。今、悔い改めてキリストを信じ受け入れて従う信仰がなければ、ユダヤ人であっても神の国から除外される。かつて神はアブラハムと契約を結ばれ、アブラハムの子孫を神の民として祝福することを約束されたことは事実である(創世記12章1~3節)。これが選民思想の起源である。だが、自分たちの父祖はアブラハムだと、それを口にできる者が救われるのではない。使徒パウロは教えた。「アブラハムへの祝福がキリスト・イエスによって異邦人に及び」(ガラテヤ3章14節)。「あなたがたがキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです」(ガラテヤ3章29節)。このようにして、神はキリストを通して、全世界からアブラハムの子孫を、すなわち、正真正銘の神の民を召し出しておられる。すると、次のことが起きる。
「人々が東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます」(29節)。これは明らかに、ユダヤ人限らず、異邦人を含めて、東西南北の世界中から神の国に救い入れられる人が起こされることを告げておられる。これらの人たちは、狭い門から入って、神の国の祝宴に連なった。これらの人たちは、悔い改め、キリスト信仰を全うした人たちである。人種、民族は関係ない。
最後に主は言われる。「いいですか、後にいる者が先になり、先にいる者が後になるのです」(30節)。「先にいる者」がユダヤ人で、「後にいる者」が異邦人という見方もできるかもしれないが、いずれ、この文脈で「先にいる者が後になる」という場合、決して良い意味で言われていないことを覚えておきたい。「先にいる者が後になる」とは、神の国の祝福から除外されてしまうことを意味しうる。これを現代の私たちに適用すればどういうことになるだろうか。一人のクリスチャンがある家を訪問した時のことであった。訪問先のその人は、昔の聖書を引っ張り出してきて広げ、みことばにたくさん線が引かれてあるページを見せて、「昔は教会に通って、こんなに勉強したんですよ」と話されたとのことだった。では今はというと、競技の途中で競技をリタイアしたのと同じ状態だった。
今日の講話は、「主よ、救われる人は少ないのですか」の質問で始まった。人々は救われる人の数の大小について好奇心を抱いていた。けれども、救いを自分のことから切り離し、頭の中だけで、こうした疑問をいじくり回しているだけなら空しい。概してユダヤ人は、自分の救いに関しては楽観的だった。主イエスはそれを知っておられた。主イエスは、「あなたは救われますか?」、「救いをあなたの問題として考えなさい」と、聞く者に「活」を入れようとしたのが、今日の講話である。だから、いきなり最初に「狭い門・狭い戸口」という表現を登場させる。そこから入ろうとする必死さ、そのことに一心に取り組む姿勢を要求する。うかうかしていてはいけないよと。そして、「おまえたちはどこの者か知らない」とか、「不義を行う者たち、みな私から離れて行け」とか、「自分たちは外に放り出されているのを知って、そこで泣いて歯ぎしりするのです」とか厳しいことばを連続して述べ、最後は「先にいる者が後になるのです」と引き締めを図る。以前ご一緒に学んだへブル人への手紙は、試練や誘惑によってキリスト信仰が途中挫折してしまわないようにと励ますために執筆された。信仰生活の後半が緩んでしまうというのは、統計的調査でも言われていることである。だから、「努める」というのはたゆまぬ姿勢でなければならない。実際、「狭い門から入るように努めなさい」の「努めなさい」は、原文では継続を表わす命令形となっている。「狭い門から入るように努め続けなさい」。
皆さんは、「うさぎとかめ」の寓話をご存じだろう。うさぎはダッシュは良かったが、途中、どうせかめには勝てるさ、と居眠りしてしまった。結果はご存じのとおりである。話をちょっとアレンジして、うさぎがかめの背中に乗って楽しようとしたものまである。かめをタクシー代わりに使ってしまう。私たちは他人の信仰でどうにかなるのではない。自分の信仰の足で立って歩むわけである。だが私たちは肉の力でがんばるのではない。そのようなことを聖書は教えていない。主イエスは人となられ、すべての点において私たちと同じように試みにあわれたので、私たちの弱さをご存じである。私たちを助けてくださるお方である。へブル人への手紙の著者は、誘惑や試練に負けないように叱咤激励した後、自分の力で頑張れと突き放すのではなく、主イエスは私たちと同じ人間になられたので私たちの弱さに同情できない方ではないことを告げた後、こう励ます。「ですから私たちは、あわれみを受け、また恵みをいただいて、折りにかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか」(へブル4章12節)。自分の弱さばかりを見つめるのではなく、主を見つめるのである。主に助けを求めることである。主が私たちの力である。
そして私たちは何よりも、主が狭い門そのものなのであることを覚えておきたい。世間では、この狭い門ということばだけが独り歩きを始め、難関試験突破とか苦難の道を歩まなければならないことだとか、狭い門が主イエス・キリストと切り離されて語られるようになってしまった。だから狭い門と聞くと、否定的イメージを持ってしまう。しかし狭い門の本体が主イエスだとわかれば、それはどんなことをしても入りたくなる門である。主イエスは愛する門、喜びの門であり、この世が用意するどんな門よりも慕わしい門となるのである。少々の苦労もいとわず入りたくなる門となるのである。主イエスはすべての人に向かって、「わたしのもとへ来なさい」と招いておられるので、ある意味、この門は狭い門ではない。だが主イエスに本当の意味で関心を持つ人はわずかで、悔い改めと信仰をもって、この招きに応える人はわずかであるので、それは「狭い門」となっていると言えよう。入るのが難しいから、それは狭い門なのではない。誰でも入れる門である。老若男女問わず、学力の差問わず、貧富の差問わず、スタミナのあるなし問わず、誰でも入れる門である。ただ、イエス・キリストという人格に自分をコミットできる方が入ることができる門である。それは十字架のもとに行くときに見出す門であるとも言えよう。この狭い門をくぐることができる人は幸いである。