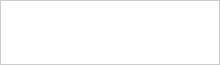今日のテーマはズバリ「神の国」である。完全に満足できる国を求めて世界旅行をした人がいるが、そんな場所は世界中どこを探してもなかったという結論に達した。では、神の国はどうだろうか。想像を絶する素晴らしい国であると思う。今、その神の国は発展途上のうちにある。今日の区分では、神の国のたとえが二つ取り上げられていて、神の国の成長ということにポイントが置かれている。
最初のたとえが言わば園芸である。園芸で楽しみにするのが成長であると思う。種を蒔く、あるいは苗を植える。芽が出て、茎が伸び、花を咲かせ、実が生り、それを楽しみに作業をしていく。実家は農家であったので、お米だけではなく、野菜や果物も多種類作っていた。実の生る木も敷地や畑に色々あった。畑に関しては、祖母がまめに毎日作業していたことを覚えている。高校、大学でも作物の栽培を学んだが、その成長は神秘のプロセスを踏むということを実感させられた。どうしてあんな種から、あんな色形の実がなるのだろうと。
次のたとえはクッキングである。クッキングもめんどうと言えばめんどうだが、作るのが好きな人にとっては楽しい作業となるわけである。私が子どもの時は、母親が「うそこきパン」と言って、小麦粉に砂糖やら卵やら何かを入れてフライパンで熱して、いわゆる膨らまないパン菓子を良く作ってくれた。パンは膨らむもので、膨らまないパンだから「うそこきパン」というわけである。
園芸のたとえにしても、クッキングのたとえにしても、今回のたとえのポイントは、美味しいかどうかということよりも、小から大へという成長にある。そのことを見ていく前に、「神の国」とは何かを整理しておこう。「国」と訳されていることばは「王の支配」という概念があることばで、「神の国」とは、「神が王として支配する国」である。神の国は、マタイの福音書では「天の御国」または「御国」と言い換えられている。一例を挙げると、マタイ4章17節では、「悔い改めなさい。天の御国が近づいたから」とある。この天の御国を、昭和時代の口語訳では「天国」と訳していた。「悔い改めよ。天国が近づいた」。この天国ということばが、けっこう独り歩きを始めてしまい、神の国の意味を狭めてしまった。人が死んで向かう世界が天国という理解が一般的である。その世界は、地上やこの体から脱した天上の霊の世界である。ここが最終目的地と言わんばかりに。この理解を浸透させてしまった一つの要因は、ギリシャ哲学である。その一つであるプラトン主義は、物質は悪、霊は善という二元論の考え方に立っていて、肉体も悪と捉える。よって、肉体という牢獄から霊が解き放たれ、霊が安らぐ理想郷を志向した。中世の教会はその理想郷を天国と同一視するようになっていった。けれども、この理解で終わっていいのかということである。聖書の教えは物質である体を悪だと言っていない。霊が天国に行って終わりとも言っていない。からだの復活を教えている。そして、その復活のからだをもって御国で生きることを教えている。また仏教圏では極楽浄土の思想があるが、この影響も大きい。天国と聞けば「極楽浄土」の世界と同一視している日本人は多いだろう。死んだ人が行くあの世、彼岸の世界、それが天国というわけである。仏教の葬式でも皆が「天国」を口にするようになった。確かに「天国」という世界はある。だがそれは、神の国の一部である。一側面にすぎない。死後の世界として天国ということばを使うにしても、聖書は誰でも彼でも天国に入るなどと教えてはいない。新約時代の教えでは、キリストを信じて罪赦されて天国に入るとなるだろう。その上で、受け止めなければならないことは、天国イコール神の国ではなく、天国はあくまで神の国の一部でしかないということである。
「神の国」は地上から天上へ行く世界というように、垂直レベルに捕らえて終わりの世界ではない。聖書において「神の国」は、この地上の歴史において漸進的に(段々と)成長しているものとして教えている。それが今日の教えである。
「神の国」については旧約時代から新約時代のスパンで捉えることが肝要である。創世記を見れば、最初の人間であるアダムはエデンの園に置かれたことがわかる。「神である主は東の方のエデンに園を設け、そこにご自分が形造った人を置かれた」(創世記2章8節)。ヘブル語で「エデン」は、「楽しい」「喜ばしい」を意味する。ところがご存じのように、アダムは神の戒めに背き、罪人となり、そしてエデンの園をはじめとする被造物世界は罪によって呪われたものとなった。エデンの園はエデンの園ではなくなってしまった。さらに、アダムたちはエデンの園から追放されてしまう。だが、神の救いの御手が動いていく。前にもお話したように、キリストは第二のアダムとして来られた。キリストの使命はエデンの園の回復、すなわち神の国を打ち立てることである。聖書の最後の書である黙示録には、エデンの園の回復の様子が終盤に描かれている。黙示録21,22章は、明らかに創世記のエデンの園が意識されている描写である。そこでは「新しい天と新しい地」と呼ばれている(21章1節)。その世界は、エデンの園の回復した世界というよりも、正確には、エデンの園以上の世界である。この新天新地が神の国の別称である。そこは、もはや、罪も、死も、呪われるべきものは何もない世界。すべてが一新され、天と地が結び合わさった世界。神とキリストが統治する永遠に滅びない世界。新エデンの園である。
「国」ということばは「王の支配」という概念をもつことばであることを先にお話ししたが、神の支配は天では完全と言えるだろう。その世界を「天国」と言っても良いだろう。だが、地上ではまだそうではない。だから、主の祈りでも、「みこころが天で行われるように、地でも行われますように」と祈る。神の支配が天ばかりではなく地でも完全となり、それが一つの世界となって、それが神の国の完成である。地上からポーンと天上に行った世界が神の国というわけではない。地上が無視されているわけではない。天上が地上に降り立ち完成を見る世界である。「私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神のみもとから、天から降ってくるのを見た」(黙示録21章2節)。この時が御国の完成である。私たちはそれまで、「御国が来ますように」と祈るわけである。
さて、当時のユダヤ人は神の国をどう考えていたのだろうか。それは日本人のように、霊がたどり着く「あの世」とは考えていなかった。全くの反対で、地上の政治的王国として待ち望んでいた。ユダヤ人は長きにわたって、諸外国からうんざりするほど圧政を受けて来た。キリスト在世当時はローマ帝国の支配下にあった。彼らが待ち望んでいたのは独立したユダヤ王国であり、諸外国に君臨するイスラエル王国である。それが彼らにとっての神の国である。彼らが待ち望んでいた神の国とは民族国家であった。地上の国家であった。死んだ人が行くあの世の世界という考えはなかった。神殿を統括していたサドカイ派に属する大祭司たちは、霊の存在や死後のいのちも信じていなかった。彼らに天国という概念はない。パリサイ派は霊の存在は信じていたが、いずれ、地上で再興される国家を待望していた。
大切なことは、聖書は神の国についてどう教えているかである。神の国を現代人が考えている意味で天国と言ってしまうことも、地上の国家と言ってしまうことも正しくはない。それらを越えた存在である。天上も地上も包括した世界である。天と地が一つとなる世界である。キリストは時至って、この神の国の王として来られた。キリストの公生涯を見ると、神の国の告知で始まり、神の国の告知で終わっている。「ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を宣べ伝えて言われた。『時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい』」(マルコ1章15節)。「ほかの町々にも、神の国の福音を宣べ伝えなければなりません。わたしは、そのために遣わされたのですから」(ルカ4章43節)。そして、昇天前の記述では、「四十日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた」(使徒1章3節)。昇天前の中心となる指針は、神の国の福音を全世界に宣べ伝えることであった。
神の国はキリストの来臨によって、小さく始まったのである。イスラエルのガリラヤ地方という軽蔑されていた片田舎で、主イエスは宣教活動を開始された。人々は神の国はいつ来るのかと待ち望んでいたが、キリストの宣教活動とともに神の国は来ていたのである。「しかし、わたしが神の指によって悪霊どもを追い出しているなら、もう神の国はあなたがたのところに来ているのです」(ルカ11章20節)。「パリサイ人たちが、神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。『神の国は、目に見えるかたちで来るものではありません。見よ、ここだとか、あそこだ、とか言えるようなものではありません。見なさい。神の国はあなたがたのただ中にあるのです』」(ルカ17章20,21節)。主イエスは、神の国はすでに来ていることを語られ、かつ、目に見えるかたちとしての国をどこかに作られたことを否定された。「国」とは「王の支配」という概念があることばだが、すなわち、主イエスの福音宣教によって、王なるキリストの支配は始まったのである。神の国はすでに到来したのである。この地上に到来したのである。そして、神の国の進展、神の国の前進、神の国の拡大が期待された。そのために、主イエスは弟子たちに神の国の宣教のビジョンを昇天前に与えることになる。「しかし、聖霊があなたがたの上に臨むとき、あなたがたは力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、さらに地の果てまで、わたしの証人となります」(使徒1章8節)。使徒の働きにおける神の国の進展を見ると、福音がユダヤ人たちの間だけではなく、異邦人にも広まっていく様を見ることができる。そして聖書の時代は終わり、時至って神の国の福音は島国日本にも届けられた。現代も神の国は漸進的に進展している。成長している。私たちは終末の時代を生きているわけだが、この地上の目に見える現象面では、罪は満ち、災害もひんぱんに発生し、健康的な世界には見えない。だが、神の国は存在している。私たちはこの神の国の成長を信じるのである。神の国の影響力は、目に見えるかたちで完全に現わされる時が来る。それは天からの支配が完全になる時である。キリストの再臨がその節目となる。その時、万物は刷新される。神の国は、現在は「すでに未だ」の世界である。だが、「すでに未だ」の世界である神の国は成長を遂げ、完全なる姿を現す時が必ず来る。その時は近づいている。だから私たちは、「御国が来ますように」と祈る。また神の国の福音を伝える。
では、たとえを見ていこう。最初のたとえは「からし種のたとえ」である(18,19節)。「からし種」は非常に小さい種として知られていた。100粒で1グラムしかないと言われている。ところが生長すると、大きいもので3メートルを越えるものが出て来る。「空の鳥が枝に巣を作りました」と言われるほどの大きさとなる。木が成長し、木の枝が伸びて、鳥が巣を作るほどになるのと似たような描写は旧約聖書にもある(ダニエル4章10~12節 エゼキエル17章22~24節)。それらは国の成長の描写である。だから主イエスのたとえを聞いて、このたとえは神の国の支配、キリストの支配が全世界に広がることのたとえであると、賢明な人は悟れる。神の国の初めは、ナザレから何の良いものが出るだろうかと、ガリラヤで始まった小さな運動にすぎなかった。しかし、それは、やがて全世界の諸族、諸国語の人々が神の支配の中に入るという運動に発展していく。そして、神の国は、ついには、キリストにあって、東から西から、南から北から、すべての民族を救いの傘下に入れるという、枝を伸ばした大きな国となる。
続くは「パン種のたとえ」である(20,21節)。「パン種」とは、小麦粉を練った固まりを膨らませるイースト菌のことである。パンを焼く前に、その生パンの一部を少し取っておいて、今度新しく練る時に、その取っておいた一部を混ぜるわけである。「パン種」そのものは、悪い意味にも用いられる。12章1節において主イエスは、「パリサイ人のパン種、すなわち偽善には気をつけなさい」と教えられた。パン種も古くなりすぎると、酸っぱくなってしまっていて、それは悪の影響力とか、悪の感化力のたとえにも使われるというわけである。この場合は、良い影響力、良い感化をもたらすものとして用いられている。このたとえの強調点は、わずかのパン種が終わりには全体に行き渡り、浸透し、広まり、膨らんで、大きな影響力をもたらすということにある。
パン種を混ぜるのが「三サトンの粉」とあるが、現代の分量で言うと、正確には38.4リットル(およそ39リットル)。人数としては100~150人分のパンである。わずかの、ひとつまみのパン種が、パンをパンたらしめ、100人分以上のパンを生成することになる。同じように、小さいものと思われたナザレ人イエスの運動体、ガリラヤの小さな共同体、それが全世界に浸透して大きな影響力をもたらすことになる。
このたとえは、私たちと無関係ではない。私たちキリストをかしらとする教会という運動体は、小さいものと思われても、全世界に大きな影響力をもたらすものである。そして、やがて神の国は全世界を支配するものとして姿を現す。その神の国は、視覚的にも、私たちを圧倒するすばらしいものとなるだろう。そのすばらしさについて少しだけ触れておくと、お話しの最初のほうで、「エデン」の意味を「楽しい」「喜ばしい」と言ったが、語源的には「豊かさ」と関係しており、「豊かな水のあるところ」が根源的意味となる。エデンからは一つの川が流れ出ていた。「一つの川がエデンから湧き出で、園を潤していた」(創世記2章10節)。それは四方を潤し、いのちを与える水となっていた。同じように、黙示録22章1,2節前半には、いのちの水の川が流れ出ている描写がある。「御使いはまた、水晶のように輝く、いのちの水の川を私に見せた。川は神と子羊の御座から出て、都の大通りの中央を流れていた」。それに続いて、いのちの木の描写が続いている。荒地とは無縁の描写である。新しいエデンには神の御座があり、そこからいのちの水の川が流れ、その周囲にはこの地上のどこにも見られない光景が広がっている。神の国の全容は明らかにされていないが、それは私たちの想像と期待をはるかに超える世界であろう。新エデンの園である。そこをキリストは王として治められる。そこには太陽も月も必要としない。キリストの栄光がすべてを照らすのである(詳しくは黙示録21,22章をご覧ください)。
この神の国は、現在は漸進的に成長している。そして、やがてキリストの再臨とともに、視覚的にもはっきりした形で姿を現すことになる。それは王である主なる神の支配が完全になる時である。
さて、私たちの役目のことも考えてみよう。私たちは神の国の民とされた。私たちは、単に天国に行くためにクリスチャンにされたわけではない。この地上での生活を、天国に行くための待合室として過ごすために召されたわけではない。「パン種のたとえ」は私たちの個人の生活にも適用できるだろう。パン種は影響を与えるものである。もし、周りと一緒になって、くさる、落ち込む、ただぶつぶつ不平を言う、ジコチュウにふるまう、それであったら古いパン種と同じである。私たちは新しいパン種として歩む。周囲に良い感化を与えるためである。私たちの役目は神の国の民として周囲の祝福となり、周囲を祝福するためである。それが神の国のスピリットである。私たちはキリストの心を心とし、地に足をつけて隣人に仕え、祝福し、福音を伝えることに心を砕いていこう。私たちはそのようにして、残された地上の人生を歩み、新しい天と新しい地という「神の国」が到来することを、楽しみにして待ち望んでいきたいと思う。私たちには未来が見えないというのではなくて、この神の国という希望があるのである。